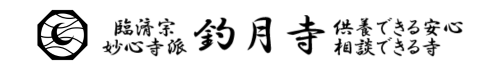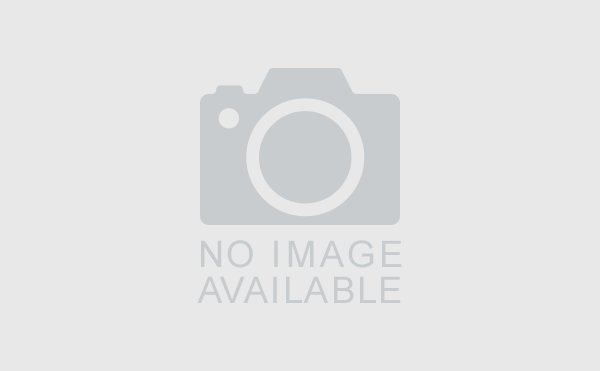お盆の総括
今年から、お盆の棚経の形式を変更しました。
昨年までは、檀家の方の自宅に伺い読経をしておりましたが、諸事情(猛暑と体がもたないのが主な要因)により「ご希望される方は本堂に位牌をお持ち頂いての読経」に変更しました。
お盆を終えて、私が感じた事を総括として書きます。
今回は、永代供養塔・樹木葬・しもかぬき墓苑を利用されている方(檀家以外の方)にも読経の案内を出しました。
読経を希望される方の中には檀家以外の方や、今まで読経に伺っていない遠方の方もおりましたが、思っていた以上に本堂での読経を希望する方が少なく(案内を出した方の約3割)、かなりショックを受けました。
釣月寺に限った事ではないですが、お盆に対する寺側の意識と、檀家の方の意識に乖離があるという事を感じ、今年は色々と考えさせられるお盆でした。
この意識というのは、世代交代による意識の変化や、時代が変わった事による意識の変化によるものが主な要因と思われます。
以下、私が感じた意識の違いです。
●寺側の考え
①お盆に棚経に伺うのは当然の事(特に新盆)で、棚経は行かなくてはならないものである
②棚経に伺うにあたり、檀家の都合は考慮しない
●檀家の考え
①家に来られるのは都合が悪い(片付けや支度など)
②お盆の為に仕事は休めないので、昼間は家にいない
③世代交代などにより、お盆をあまり意識しなくなった
本堂での読経を希望された方に話を聞いてみると、「自分の都合の良い時に本堂で読経をして貰えるのは良い事である」「身内と日時を調整して釣月寺に集合という事にすれば、身内も集まりお盆の供養もできて良い」という意見があった一方、「わざわざ位牌を持っていかなくてはならいのであれば、行かない」という意見もありました。
今回は、新盆であっても読経を希望する人は少なかったです。
この様な現実を踏まえると、お盆の読経は先祖の供養が主な目的ではあるが、こちらが思っている程檀家の方はお盆を意識しておらず(春彼岸、秋彼岸、暮と同様にお墓参りのみ)、自宅に伺っての読経を押し付けていた面もあると気づき、お盆の宗教的な意味が薄れていくのは時代の流れで仕方ない事だとも思い知らされました。
来年のお盆の対応時間は、今後検討していく課題です。