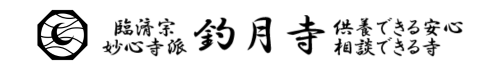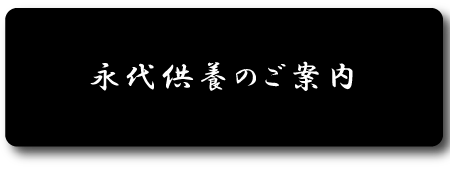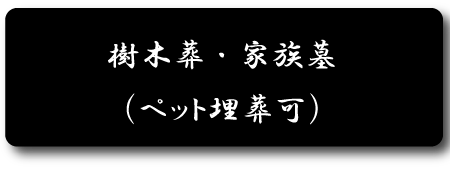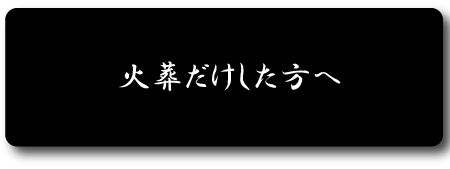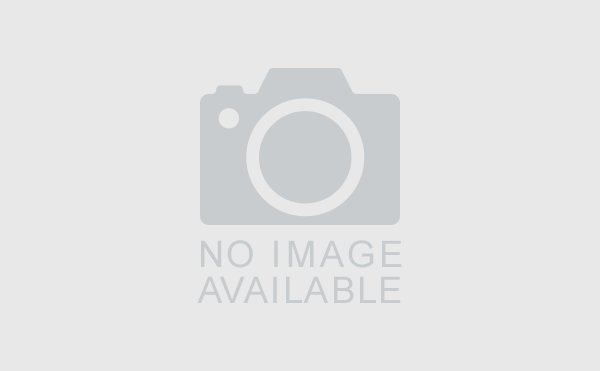「兼務寺院の増加」
このコラムでも、寺院の後継者問題や寺院消滅について書きましたが、住職がいくつかの寺院を掛け持ちする兼務寺院が増加しています。
後継者がいないから無住(住職がいない事)になる、後継者がいても生活していけるだけの収入がないという理由があげられます。
キリスト教の教会においても、同じように複数の教会を掛け持ちしている割合が増えているそうです。
住職というのは「住む職」と書くので、常駐するのが当然の事ではありますが、無住寺院の場合、維持管理は役員の方がするのが常であり、宗費(本山への上納金)も役員の人が負担しているという寺院もあります。
臨済宗・黄檗宗に関してですが、兼務寺院が占める割合は、北海道9,5%、東北28,2%、関東26,3%、中部35,9%、近畿36,3%、中国34,9%、四国41,1%、九州沖縄29%となり、全国で見ると33,8%という調査結果があります。
兼務する理由としては多い順に「先代が兼務していて、それを引き継いだ」「当該寺院の檀家から兼務を依頼された」「当該寺院の住職から兼務を依頼された」「自ら望んで当該寺院を兼務した」というものでした。
いくつかの寺院を兼務すれば、収入が増えていいと思う人もいると思いますが、兼務寺院の殆どは1カ寺あたりの檀家が10件未満なので、兼務寺院をかかえていても寺院の維持管理には費用がかかる為、金銭的、体力的に大変な事しかありません。
半径50キロの範囲に14件を兼務している住職もいるそうです。
また、住職個人の資金を寺院の維持管理に使用するのも珍しくない事です。
沼津市内の例をとっても、無住寺院は今後増えていくのは確実なので、これからは「寺じまい」も珍しい事ではなくなります。