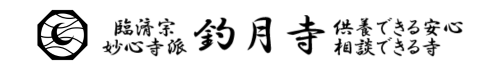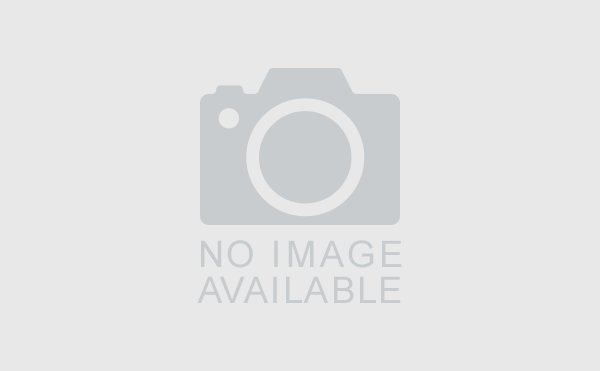「葬儀の形式」
(一財)日本消費者協会「第12回葬儀についてのアンケート調査報告書」
(2022年3月)の調査結果を、5回に分けて取り上げてみます。
第3回目は、「葬儀の形式」です。
多くの方が実感している事ですが、コロナ禍以降一般葬が減少し、家族葬が割合としては増えています。
葬儀の形式の推移として、2014年~2016年、2017~2019年、2020年~を以下の項目で比較してみます。
①一般葬
②家族葬
③直葬
④一日葬
2014年~2016年は、①56.6%、②35.4%、③2.0%でした。
一日葬はまだ数が少ないので調査対象外です。
2017年~2019年は、①44.6%、②50.0%、③2.2%、④2.2%でした。
2020年~は、①25.6%、②64.8%、③3.2%、④2.5%でした。
直葬や一日葬の割合は、地域性もあるので都市部では割合が多いと思われます。
以前は、「会葬者は身内のみ=密葬」と呼ぶ事がありましたが、密葬はその後に本葬儀を行う事が前提であるので、イメージとしては昔の密葬が現在の家族葬にあたると思います。
住職が遷化(亡くなる事)した際には、今まではまず密葬を行い、本葬儀である津送(しんそう)を後日行っていましたが、最近は住職の葬儀であっても、密葬と本葬儀はせずに1度の葬儀で済ます事も増えてきました。
一般の方の葬儀が簡素化してきている現状において、住職とはいえ昔と同じように大々的に葬儀を行うのは現実的ではないと考える住職もおり、昔からの慣例だからという理由では理解を得る事は難しくなりました。