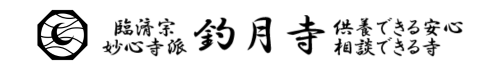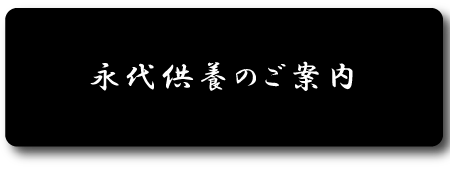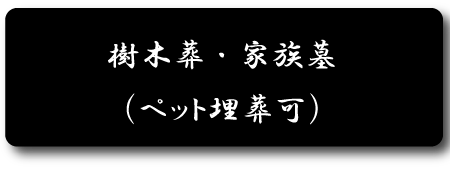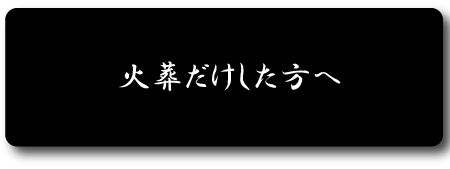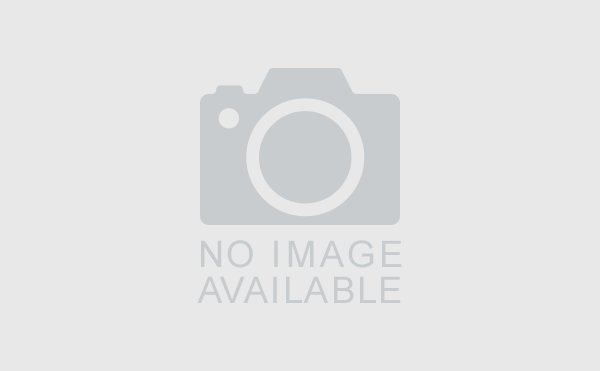「増える導師1人の葬儀」
前回に引き続き、今回もコロナ禍以降の葬儀の変化について書きます。
今回は、出仕僧(役僧)の減少についてです。
葬儀の際、導師以外のヘルプの僧侶の事を役僧と言いますが、コロナ禍以降役僧の減少が顕著です。
私が役僧の減少に関して感じたのは、コロナ禍よりもだいぶ前の10年程前からになりますが、大都市部においてはさらに前から葬儀は導師のみだったそうです。
それぞれの役僧には役割があり、印鏧(いんきん)、鈸(はち)、懺法太鼓(せんぼうだいこ)という仏具を鳴らし、邪気を払い清めるという謂れがあります。
また多くの役僧を頼んで、故人をこの世から送り出す事が功徳に繋がると考えられていましたが、現在ではその様な意識も薄れ、葬儀社が台頭してきた事による葬儀費用の増加などにより、役僧を頼む、役僧を頼まれるという事はほぼなくなりました。
修行から帰ってきたばかりで経験が浅い時においては、経験を積むというメリットがあり、役僧に呼ばれたからこちらも役僧に呼ぶという、ウィンウィンの関係がお互いにありました。
この役僧での収入がかなりのウエイトを占めている檀家の少ない寺院においては、役僧に頼まれないという事が寺院運営に大きな影響を及ぼす事もあります。
また、本堂での葬儀は導師1人でも行うが、葬儀会館での葬儀においては、施主に役僧を頼んで貰うという寺院もあるそうです。
役僧に頼まれたいが為に、檀家の多い寺院に対して胡麻を摺る僧侶もいました。
このコラムでも、寺院の将来は前途多難であり、「檀家が少ない=資金力がない」という事で、自力で何とかしていかないと厳しいと書きましたが、他の寺院に頼らない寺院経営というのを考えていかなくては生き残れない時代になりました。
これからは、それぞれの僧侶の手腕が問われる時代です。