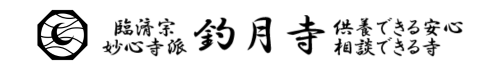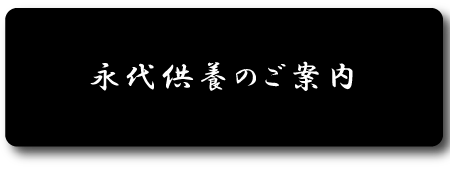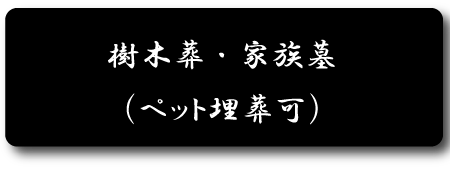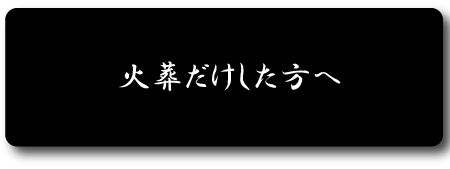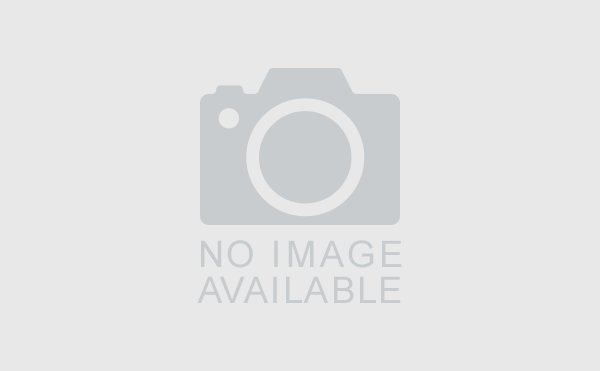「地域による一日葬の認識の違い」
仏事に関して、地域による慣習や違いは意外と多いです。
遺骨に関して大まかに分けると、関東は全骨納骨(全ての遺骨を持ち帰り、自分の墓所に納める)ですが、関西は一部納骨(喉仏などの一部を持ち帰り、自分の墓所に納める)という違いがあります。
今回は、一日葬に関して首都圏と関西の認識の違いについて書きます。
コロナ禍以降、葬儀の規模の縮小化は全国的な傾向で、「一日葬」「家族葬」が増加し定着する様になりました。
しかし、一日葬などの葬儀の簡素化は、首都圏が8割を超えているのに対し、関西は3割にも満たないという調査結果があります。
首都圏で一日葬が多い理由としては、コロナ禍以前から一日葬が選択肢のひとつであった事、通夜と葬儀の役割に明確な区別があった事などが挙げられます。
首都圏において、通夜は社会的な繋がりを持つ人のお別れの場、葬儀・告別式は家族・親族のお別れの場という認識がありましたが、コロナ禍で社会的な繋がりを持つ人の会葬がなくなり、通夜を行う意義が失われ一日葬が増えたそうです。
一日葬が増えたとはいえ、通夜の意味・役割、葬儀・告別式の意味・役割があり、一日葬はとんでもないと言う僧侶もいます。
以前は、通夜が終わってから翌日の葬儀・告別式までの間、遺族が火を絶やさないように線香やローソクを替えるという「寝ずの番」というのがありました。
寝ずの番には、亡くなった方が生き返るかも知れないという意味合いもありました。
以下、ウィキペディアからの引用です。
「殯(もがり)とは、日本の古代に行われていた葬送儀礼。死者を埋葬するまでの長い期間、遺体を納棺して仮安置し、別れを惜しみ、死者の霊魂を畏れ、かつ慰め、死者の復活を願いつつも遺体の腐敗・白骨化などの物理的変化を確認することにより、死者の最終的な「死」を確認すること。」
しかし、首都圏での一日葬の増加の背景を踏まえると、一日葬が増えていくのはやむを得ない事です。
同様に、コロナ禍以降家族葬が増加した背景には、会葬者を身内などに限定する事により、世間体を気にする必要がなくなった事や、身内同士で納得できるお別れができるという事が挙げられます。
通夜・葬儀に関して、時代の変化、意識の変化によって変わらざるを得ない事もあり、その様な実状を踏まえてどの様にしていけばいいのか?を私たち僧侶は大いに考えていく必要があります。